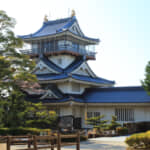破談になりかけていた家康と旭姫の「結婚」
史記から読む徳川家康㉞
9月3日(日)放送の『どうする家康』第34回「豊臣の花嫁」では、長年の老臣・石川数正(いしかわかずまさ/松重豊)出奔(しゅっぽん)後の徳川家の様子が描かれた。着々と天下人への足場を固める豊臣秀吉(とよとみひでよし/ムロツヨシ)の前に、次第に追い詰められた徳川家康(とくがわいえやす/松本潤)は、ある決断をする。
石川数正の真意を知った家康は天下取りを断念する

岐阜県白川村に残る帰雲城跡の石碑。1585(天正13)年11月の大地震により、付近にあった帰雲山で山崩れが発生。城はもちろん、城主を務めていた内ヶ島氏理やその一族、家臣、牛馬がまたたく間に埋没し、内ヶ島氏は滅亡した(『三壺聞書』)。
重臣・石川数正の裏切りに言葉を失う徳川家だったが、豊臣秀吉の脅威から家を守るべく、上洛して秀吉に臣従するか、多大な犠牲を覚悟して合戦におよぶか、徳川家康は二者択一の選択を迫られることとなった。
家康が思い悩むなか、巨大な地震が発生する。天正(てんしょう)地震と呼ばれるもので、被害は広範囲におよび、秀吉も家康も戦どころではなくなった。
合戦より復興を選んだ秀吉は、家康のもとに自身の妹である旭姫(あさひひめ/山田真歩)を正室として送りつけることで懐柔を図った。それでも家康が上洛しないと見るや、母親も人質代わりに送るという。
徳川家では、数正不在で重臣たちによる評定が行なわれた。いくら話し合っても、秀吉に対する敵対心はもとより、本多忠勝(ほんだただかつ/山田裕貴)と榊原康政(さかきばらやすまさ/杉野遥亮)の家康を天下人にするという思いは頑なで、武力衝突は避けられそうにない。
そこへ家康の側室である於愛(おあい/広瀬アリス)が評定場に現れる。於愛は数正の残した仏像などから推測した、出奔した数正の真意を伝えに訪れたのだった。一同は不器用な数正の思いに接して、涙ながらに家康による天下取りを断念することにした。
こうして家康は、秀吉の傘下に降るため、上洛を決意したのだった。
「家康上洛」に反対したのは酒井忠次だった
石川数正が出奔した1585(天正13)年11月は、徳川家康にとって、三河(現在の愛知県東部)、遠江(とおとうみ/現在の静岡県西部)、駿河(するが/現在の静岡県東半部)、甲斐(現在の山梨県)、信濃(現在の長野県)の五ヵ国の経営がようやく軌道に乗りかけた頃だった。
数正出奔の報を受けた家康は同月16日、動揺しないよう家臣に指示を出している(『家忠日記』『神君御年譜』「下条文書」)。
同月28日には、織田長益(おだながます)、滝川雄利(たきがわかつとし)らの訪問を受け、家康は上洛を促された(『家忠日記』『神君御年譜』)。徳川と羽柴の両軍は一触即発の状態であり、戦いを避けようとさまざまな人物が動いていたようだ。
その翌日となる同月29日、巨大な地震が近畿・東海地方を襲った。京都では三十三間堂(京都府京都市)の仏像600体ほどが転倒するなどの被害が報告されている(『宇野主水記』)。この地震は同年末の12月23日頃まで毎日、余震が続いたというほどの規模だった(『家忠日記』)。
- 1
- 2